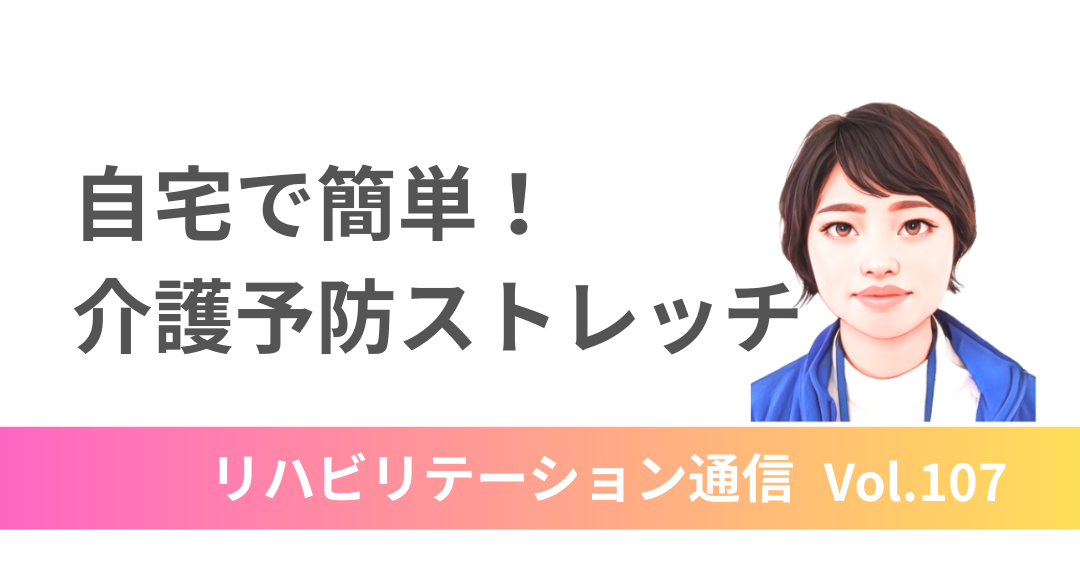はじめに
「歳をとるにつれてつまずきやすくなった」
と感じていませんか?
もしかしたら筋肉の柔軟性が低下しているかもしれません。
筋肉が硬くなると関節が動きにくくなるため、転倒やケガを引き起こす恐れがあります。
そんな方に行ってもらいたいのが、ストレッチです。ストレッチは、筋肉の柔軟性を改善する効果があります。
この記事ではストレッチを行うメリットや注意点、すぐに行えるメニューをご紹介します。ストレッチを行う習慣をつければ、転倒予防につながります。
ストレッチを行うメリット
転倒予防につながります
ふくらはぎの筋肉「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)」が硬くなって、つま先が上がりにくくなったとしましょう。その場合、歩くときにつま先が上がらないので、地面につまずきやすくなって転倒の危険性が高まります。
しかし、ストレッチによって下腿三頭筋の柔軟性を高めておけば、つま先が十分に上がって安定した歩行が可能となります。このように、ストレッチは転倒予防にとっても大切なのです。
姿勢の改善が期待できます
日常生活で座っている姿勢が続くと、股関節の前面についている「腸腰筋(ちょうようきん)」と呼ばれる筋肉が硬くなります。腸腰筋の筋肉が硬くなると股関節が曲がって、姿勢がまっすぐ伸びにくくなり、やがて猫背や円背となるケースもあります。
ストレッチによって腸腰筋の筋肉の柔軟性を高めれば、股関節の可動域が確保されて姿勢改善につながります。いつまでもキレイな姿勢をキープしたい方は、ストレッチの継続をおすすめします。
リラックス効果がある
そのほか、ストレッチにはリラックス効果があるともいわれています[3]。ストレッチによって全身の筋肉の柔軟性を高めると、「副交感神経」の活動が優位に働きやすくなるからです。夜にストレッチを行えば自律神経が副交感神経に切り替わり、質の高い睡眠をとりやすくなります。
ストレッチで注意したいポイント
さまざまなメリットのあるストレッチですが、適切な方法で行わないとかえって逆効果となることもあります。そこで、ストレッチする際に注意したいポイントについてご紹介します。
反動をつけて行わない
ゆっくりと20秒以上の時間をかけて行うように心がけましょう。
呼吸を止めて行わない
呼吸を止めながらストレッチをすると身体が緊張して、筋肉を十分にリラックスできなくなります。また、呼吸を止めていると血圧が高まりやすくなるので、体に負担がかかりやすくなります。
痛くなるまで伸ばさない
痛くないけれど、筋肉がのびているなと感じる気持ちのいい程度に伸ばしましょう。
上半身のストレッチ
【胸郭を広げるストレッチ方法】
胸郭の筋肉をストレッチして、呼吸をスムーズにする方法です。

1. イスに座って両手を組む
2. 両手をゆっくりと上げる
3. ムリのない範囲まで上げたら、ゆっくりと下ろす
4. 2~3の手順を繰り返して10回×2セット行う
【体幹を捻じるストレッチ方法】
体幹周囲の筋肉をストレッチする方法です。

1. イスに座って背筋を伸ばす
2. 両手を組んだ状態で体幹を右方向に回す
3. 右方向に回した後、反対の左方向に回す
4. ゆっくりと姿勢を元に戻す
5. 2~4の手順を繰り返して10回×2セット行う
【身体の横を伸ばすストレッチ方法】
体幹の横についている筋肉をストレッチする方法です。

1. イスに座って両手を組む
2. 両手を可能な範囲で上げる
3. ゆっくりと右方向に身体を傾ける
4. 右方向に傾けた後、反対の左方向に傾ける
5. ゆっくりと姿勢を元に戻す
6. 3~5の手順を繰り返して10回×2セット行う
【背筋を伸ばすストレッチ方法】
身体を丸めて背中や腰の筋をストレッチする方法です。

1. イスに座って背筋を伸ばす
2. 身体を前に丸めて顔を膝に近づける
3. ムリのない範囲まで丸めたら、ゆっくりと姿勢を戻す
4. 2~3の手順を繰り返して10回×2セット行う
下半身のストレッチ
【膝裏の筋肉のストレッチ方法】
膝裏の筋肉である「ハムストリングス」をストレッチする方法です。

1. イスに浅く座り、片方の足は伸ばしておく
2. 伸ばした足に向かって20秒ほど身体を前に傾ける
3. ゆっくり姿勢を戻す
4. 次は反対側の足に交代して、再び20秒ほど身体を前に傾ける
5. 2~4の手順を繰り返して左右で2セット行う
【ふくらはぎの筋肉のストレッチ方法】
ふくらはぎの筋肉である「下腿三頭筋」をストレッチする方法です。

1. 立った状態で両手は壁や手すりにつける
2. 反対足の膝を伸ばした状態で後ろにする
3. アキレス腱を20秒ほど伸ばす
4. 次は反対足に交代して再びアキレス腱を20秒ほど伸ばす
5. 2~4の手順を繰り返して左右で2セット行う
これらのストレッチを行っている途中に痛みが現れたら、ムリせず中止してください。
また、今回紹介した回数や秒数は目安なので、難しい場合は自分にあった内容に調整して
みましょう。
 今回の執筆者:作業療法士 松本 綾華(まつもと あやか)
今回の執筆者:作業療法士 松本 綾華(まつもと あやか)
昨年9月に育児休業から復職し、回復期リハビリテーション病棟で勤務しています。
4人の子供の話を温かく聞いてくださる患者様にいつも感謝しています。
リハビリテーション通信 バックナンバー
通所リハビリ Instagramはこちらから☟