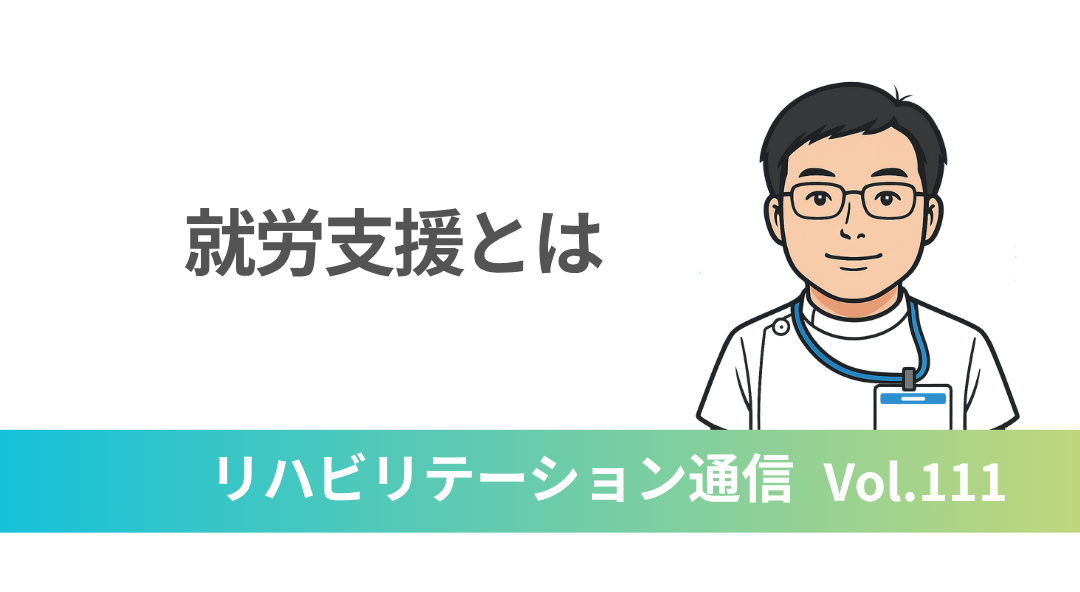こんにちは。今回のリハビリテーション通信では、私たち作業療法士の仕事のひとつでもある【就労支援】についてご紹介いたします。
はじめに
就労支援は、障がいを持つ人が就労するために必要な支援を行うサービスです。患者様・ご家族が治療と仕事の両立を図る上で、多くの場合、医療と職域間の連携が必要です。そこで、【患者様・ご家族】と、【医師・社会福祉士などの医療側】と、【産業医・衛生管理者・人事労務担当者などの企業側】の3者間の情報共有を図り、就労支援を行います。

就労支援の種類
就労移行支援
就労移行支援は一般就労を希望する人を対象としています。対象年齢は原則18歳〜64歳までですが、65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日までに就労移行支援の支給決定がある人は例外として利用できます。
具体的には、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練、生産活動や職場体験などの機会の提供、求職活動に関する支援、障がいの適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着のために必要な相談などを実施します。
就労継続支援A型
就労継続支援型とは、障害者総合支援法で定められた国の就労支援サービスの一つです。病気や障がいなどにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓練を実施するサービスです。障害者総合支援法で定められた国の就労支援サービスの一つで、事業所と利用者が雇用契約を結ぶため「雇用型」とも呼ばれています。
就労継続支援A型では、さまざまな仕事に携わることができます。パンやお菓子の製造、手芸品の作成、カフェやレストランでの接客、商品の梱包・発送、Webデザイン、工場での加工、農作業、清掃などがあります。
就労継続支援B型
病気や障がいなどがあり一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供と職業訓練をおこないます。事業者と利用者との間で雇用契約を結ばないため、「非雇用型」または「福祉的就労」とも呼ばれています。
就労継続支援B型では、就労経験を積むために様々な作業を行います。作業内容は、受け入れ先の法人によって異なります。一例として、法人が販売しているパンやお菓子などの製造、畑作業などが挙げられます。
就労定着支援
就労定着支援は、就労継続支援や就労移行支援、自立訓練サービスなどを経験して一般就労した人が対象です(障がい者雇用枠での就労を含む)。
各事業所の担当者が月1回以上の頻度で障害のある方と対面で話し、現在の職場での環境や生活リズムなどを聞き、どのような課題があるのかを把握します。
作業療法士の関わり
仕事の聞き取りを行い、障がいの種類や程度、そして個人が抱える課題に応じて、身体機能の改善、社会参加の促進、自己実現のためのサポートを行うことで、就労に繋がる能力を養います。
具体的には、以下の内容が挙げられます。
職業評価
将来の就職に向けて、仕事や対人関係等の適性、職場で必要な支援等を明らかにすることが求められます。施設内での作業や企業での実習は、体験や準備訓練としてだけでなく、アセスメントの視点を持って行うとともに、就労移行支援事業所として「何をどのように見るのか」を整理したアセスメントの方法や手段を備えておくことが求められます。
職業指導
障害の種類や程度に応じた就労の進め方や、職場での注意点などを指導します。
「職場適応援助者」によるものに限定せず、障害のある人が職場に適応するため、就職初期に就労移行支援事業の職員等が行う支援全般を指します。内容的には、仕事の自立のための支援のほか、ナチュラルサポートの形成、マッチングの再調整などが含まれます。
職業訓練
就労に必要な知識や技能を習得するための訓練を提供します。
職場復帰を目指した就労支援の具体例
入院されている患者様が、退院後に職場復帰を目指している場合、就労支援はどのような過程をたどるのでしょうか。以下にその流れを記載します。
①アセスメント
患者様、ご家族様と面談を行い、就労に関する希望、計画を行います。
②身体機能の評価
患者様の筋力や体力等を評価します。
③職場との話合い
職場の方とどのような動作、能力があれば職場復帰が可能か話し合いを行います。
患者様自身やご家族様にも立ち会っていただく場合があります。
④カンファレンス
患者様ご本人も含め、医療チームで身体機能や病態について検討し、課題の抽出のほか訓練方法や治療目標設定を行います。
⑤職場での実際の動作の確認
リハビリテーションスタッフが患者様と職場へ同行し、必要な動作を行えているか評価を行い、再度訓練方法、目標設定を行います。
⑥職場復帰前の話し合い
④で課題となっていたことが改善しているかどうかを検討し、目標に到達していない場合は、異なる部署での仕事が可能かどうかを確認します。
課題が改善され、目標に到達している場合は、職場復帰の時期や就業時間を職場の方と患者様、医療スタッフで話し合い、決定していきます。
⑦職場復帰
職場復帰の際には、医療チームが考える注意点などを患者様ならびに職場の方にお伝えします。
おわりに
病気や怪我で障がいを持ってしまうと就職は難しいと考えてしまいますが、様々な支援を受けることができます。諦めずにリハビリテーションを行い、社会に出ることも大切なリハビリテーションだと思います。
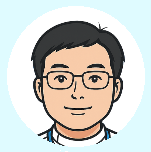 執筆者:作業療法士 岩佐 明
執筆者:作業療法士 岩佐 明
障がいを持つと何もかもあきらめないといけないわけではありません。リハビリテーション職として、患者様1人1人にあったリハビリテーションを提供できるよう日々研鑽を積んでいます。
リハビリテーション通信 バックナンバー
通所リハビリ Instagramはこちらから☟