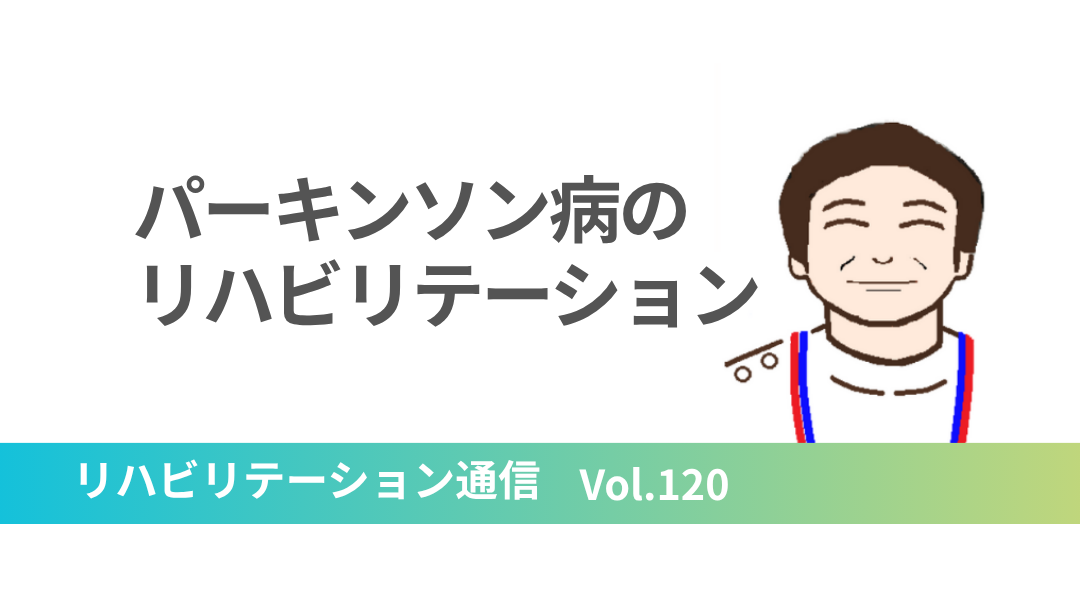はじめに
パーキンソン病は、振戦、動作緩慢、強直、姿勢反射障害といった運動機能の症状に加え、便秘、頻尿、発汗、起立性低血圧、うつ、意欲低下などの非運動性症状も生じる病気です。振戦とはふるえのことで、例えば、動作中はあまり感じなくても、静止時に手の震えが生じることがあります。また、動作がゆっくりになり、椅子に座ろうと近づいた際に小刻みな足運びになったり、足のステップが出にくくなったりします。姿勢反射障害は、
リハビリテーションについて
前述の運動機能の症状に対して、以下のリハビリテーションを行っていきます。
1. ストレッチ・筋力増強訓練
筋強直などにより筋肉が硬くなり、関節の可動域が狭まる症状に対し、筋肉を伸ばすことで関節可動域の維持・改善を図ります。また体幹や下肢の筋力を鍛えることで、転倒防止などに役立てます。特に体幹の動きに対しての安定性が得られることによって、姿勢反射障害などを抑えられます。
2. 日常生活動作訓練
段差や階段の昇降、着替えなどの細かい動作、トイレや入浴動作をスムーズに行えるよう改善していきます。手指などの振戦が生じると動作が行いにくくなりますが、しっかりと反復しての運動や動作を行うことで、生活動作の改善が見込まれます。
3. 基本動作訓練
起き上がり、寝返り、立ち上がり動作の困難さを改善していきます。特に、起き上がり動作は腕の力で引き上げがちですが、体幹の回旋運動や、頚部の動きを心がけることで改善も認められます。
起き上がり動作が難しいと感じる方は、まずはぜひ頭部・頚部の動きを向きたい方向に先行させて、起き上がる際には自身のおへそや、足を降ろしている動作を目で確認しながら起き上がってみて下さい。
4. 歩行訓練
すくみ足や小刻み歩行を改善し、転倒予防を図ります。近年ではリズムよく歩行練習が可能な歩行アシスト機器の利用や、適切な歩行補助具を使用することで歩行の改善が期待できます。
「1、2、1、2、」と自身で声を出しながらの歩行も効果的です。このときに気をつけることは、①慌てないこと ②座る際に何かに捕まるときは手を伸ばす前に一歩足を前に出すこと ③把持物を掴むタイミングの目安は肘がちょっと伸びるぐらいです。肘が伸びきってしまうのは良くありません。
5. 呼吸訓練
胸郭などの動きの減少に対し、しっかりと深呼吸を行います。この時の上肢は大きく息を吸うように横に手を広げると尚いいです。
6. 嚥下訓練
飲み込みの訓練を行い、誤嚥性肺炎の予防や、顔面筋に生じる症状への対応も行います。
パーキンソン病は進行性の疾患ですが、早期から適切なリハビリテーションを行うことで日常生活動作を維持することが可能です。また、ご自身での自主訓練も重要であり、リハビリテーションの効果を持続させるために積極的に取り組むことが大切です。
絵本などを声を出して読むこともおすすめです。口の筋肉や声帯などをしっかりと使ってあげましょう。
自主訓練について
● 歩行が安定している方
できる範囲で散歩をしたり、椅子の背もたれを持って立ち座りを繰り返したりしてください。一緒に歩いてくれるパートナーの方や、ご家族がいれば一緒に歩いてください。その際は杖や、歩行補助具など使用して大きく手を振りながら歩いてください。
● 立つとふらつく方
座って行う上肢の運動も効果的です。腕を大きく横に広げたり、そこからゆっくりと体幹をひねったりすることで、ストレッチ効果や体幹の可動域拡大に繋がります。寝返りや起き上がり動作には体幹の回旋運動が必要です。また、大きく腕を開いて体の前で手をたたく様に勢いよく手を合わせてください。大きい音が鳴るようにしてみてください。どうしても動きが小さくなり、ゆっくりとなるため、こういった運動も動きの目安となるため効果的です。
● 寝た状態が安全に運動できる方
横になった状態でも、座ったときと同じように腕を上に上げたり、横に大きく広げたりしても構いません。動きが小さくならないよう、しっかりと大きく体操することを心がけてください。また、両膝を曲げて、腕をまっすぐに上げ左右に頭の方向を向いて見て下さい。寝返り動作の練習になります。頭の方向に意識することでその向きに動きやすくなります。
おわりに
パーキンソン病は進行性の病気であり、多くの不安を抱えます。ご本人だけでなく、ご家族の理解も必要です。ゆっくりとした動きになることに対し、理解を持って接してください。一人で悩まず、かかりつけ医などに相談しましょう。
病気を恐れず、より長く安全にQOLを維持しながら生活できることを目指していきましょう。

【執筆者】
認定理学療法士(代謝)、日本糖尿病療養指導士 湯浅雅史
15年以上病院、施設などでリハビリテーションを行ってきました。地域の介護予防活動なども行っています。地域の医療を支えられるよう日々精進しています。
【湯浅雅史 理学療法士の執筆・関連記事】
・糖尿病と認知症
・当院回復期リハビリテーション病棟のご紹介
・世界糖尿病デー
・ウォーキング|避難所まで歩いてみよう
・「リハビリテーションとマッサージは違う?」
・「リハビリテーションって?」
■ リハビリテーション通信 バックナンバー